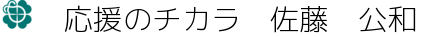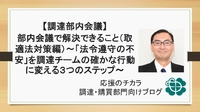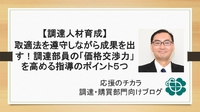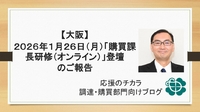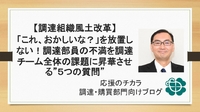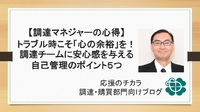- ホーム
- ブログ
- 「部下育成」関連記事
- 【マネジャー向け】「部下を教えすぎる」が良くない理由3つ
【マネジャー向け】「部下を教えすぎる」が良くない理由3つ

- なんとか部下を一人前にしたいから熱心に指導しているけど・・・。
- 部下がなかなか成長しないので困っている・・・。
- 指導しているのにうまくいかない理由が知りたい!
一生懸命指導しているのに成長しない部下、どうしたらいいか悩みますよね。もしかしたら、「教えすぎ」が原因かもしれません。
今回は、「部下を教えすぎると良くない理由」「教えすぎてしまう理由」「教えたい!と思ったときにしてほしいこと」についてお伝えします。関わり方をほんの少し変えるだけで部下の行動が変わってきますので、ぜひご覧ください。
【マネジャー向け】「部下を教えすぎる」が良くない理由3つ
「部下を教えすぎる」が良くない理由
まず、「部下を教えすぎる」が良くない理由について見ていきましょう。
理由① 自分で考えなくなる
1つ目は、自分で考えなくなることです。
部下の仕事ぶりを見て、「こうした方がいいよ」と細かく指示を出してしまうことはないでしょうか。あれこれ口出ししすぎてしまうと、部下は「うまくいかなかったら教えてもらえばいいや」と思い、自分で考えなくなってしまいます。新人のうちはそれでもいいのですが、入社して2年目、3年目と時間が経ち、そろそろ一人で動いてほしいなと思っても、自分で考えて動くことをしてこなかったので苦労してしまいます。つまり、「指示待ち部下」を作り出す原因をつくってしまっているのです。
理由② モチベーションが低下する
2つ目は、モチベーションが低下することです。
口出ししすぎると「やらされ感」が強くなります。「やらされ感」が強くなると自分なりに工夫してやってみようという意欲が低下しますので、「もっと仕事ができるようになりたい!」「成長したい!」という気持ちがなくなっていきます。「教えすぎ」が、部下自身で答えを見つけるという機会を奪っているということでもあるのです。
理由③ 教えたやり方が部下に合わない場合がある
3つ目は、教えたやり方が部下に合わない場合があることです。
部下に教えるときのことを思い出してほしいのですが、何を元にして教えていますでしょうか。「自分がやってみてうまくいったこと」を元にして教えていないでしょうか。もちろん、そのやり方が合う部下には問題ありません。しかし、そのやり方が合わない部下もいるのです。真面目な部下ほど、「教えてもらったことができない自分がダメなんだ」と自己嫌悪になってしまうものです。
教えすぎてしまう原因
次に、教えすぎてしまう原因について見ていきましょう。
原因① 早く一人前になってほしい
1つ目は、早く一人前になってほしいことです。
「会社から求められている成果を上げなければいけない。そのためには部下育成に時間をかける余裕がない。だから早く一人前になってほしい。」そんな気持ちが強いと教えすぎてしまうものです。「プレーイングマネジャーなのであまり時間をかけられない」「抱えている部下が多くて、一人一人じっくり時間をかけて話ができない」といった思いをお持ちの方もいらっしゃいます。
原因② 親切心が強い
2つ目は、親切心が強いことです。
「人から相談されたら答える」「困っている人がいたらサポートする」といった性格的なものです。以前は私も同じタイプでした。でも、親切心で教えすぎてしまうと、部下が自分に依存してしまっているということに気がつきました。その性格自体は素晴らしいのですが、部下を育成するという点でみたときには、接し方を工夫する必要があります。
原因③ 任せることに苦手意識がある
3つ目は、任せることに苦手意識があることです。
部下に任せることで「ちゃんとできるか心配だ」「失敗したときにフォローするのが大変だ」といった気持ちがあると、つい口出ししてしまうものです。まったく失敗しないで成長できる人はいません。部下が成長するためには、「失敗したら次はどうすべきか考えて行動する」機会も必要です。
「教えたい!」と思ったときにしてほしいこと
では、「教えたい!」と思ったときにしてほしいことについて見ていきましょう。
してほしいこと① すぐに答えを教えない
1つ目は、すぐに答えを教えないことです。
「この件、どうしたらいいですか?」と聞いてきたらすぐに答えを教えず、
- 「〇〇さんはどうしたらいいと思う?」
- 「〇〇さんにできるようになった欲しいから一緒に考えてみようよ。」
という会話を始めましょう。
詳しくは、「指示待ち部下を自立させる3つのステップとは?」をご覧ください。
指示待ち部下を自立させる3つのステップとは?
自分で考えて行動することが苦手な部下がいる・・・。周りに教えてくれる先輩がいないと固まってしまう・・・。指示待ち部下が自分で考えて行動できるようにさせたい!このような悩みをお持ちのマネジャーの方へ。指示待ち部下とどう接したら自立させること...
してほしいこと② 部下の成長を楽しむ
2つ目は、部下の成長を楽しむことです。
部下の成長を楽しむというのは、「部下ができるようになったことを喜べるようになること」です。部下の仕事の結果ばかり気を取られていないでしょうか。そうなると、「できたら当たり前」「できなければダメ」という意識が強くなってしまうので、部下ができるようになったことを喜ぶ余裕がありません。ときには部下のできるようになったことに目を向けて、それを伝えてみましょう。部下は「できるようになったこと」よりも「これからすべきこと」に意識が向きがちです。それとなく「以前は苦手にしていたことができるようになって成長したね」と声かけすると、部下のモチベーションがアップして、教えられる前に自分から行動しようという気持ちが出てきます。
してほしいこと③ 部下の目線に立って接する
3つ目は、部下の目線に立って接することです。
部下の目線に立つとは、「部下と同じ時期の自分はどうだったかを思い出す」ことです。「よく考えたら、自分もよく失敗していたし、教えられたことを理解してできるようになるのに時間がかかったよな」といったことを思い出すことができれば、もう少し時間をかけてじっくり部下と向き合ってみようかなと思えるようになります。
まとめ
- 部下を教えすぎると良くない理由は、「自分で考えなくなる」「モチベーションが低下する」「教えたやり方が部下に合わない場合がある」
- 部下を教えすぎてしまう原因は、「早く一人前になってほしい」「親切心が強い」「任せることにには苦手意識がある」
- 「教えたい!」と思ったときにしてほしいことは、「すぐに答えを教えない」「部下の成長を楽しむ」「部下の目線に立って接する」
自分の思った通りに部下を動かしたいというコントロール欲があると、「部下に教えることで思い通りに動かしたい」という気持ちが出てくるものです。そんなコントロール欲が出てきているなと思ったら、すぐに教えてようとしないで、ひと呼吸置いてから接してみましょう。
新型コロナウイルスの影響が続く中、人事部が積極的に従業員のモチベーション向上に関わり、従業員満足度の向上につなげていきたいとお考えの人事部様、研修担当者様向けに「部下のモチベーションアップ」研修に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
ご予約・お問い合わせ関連エントリー
-
 【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
-
 【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
-
 【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
-
 【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
-
 【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら