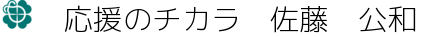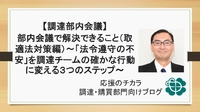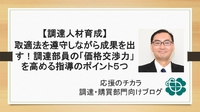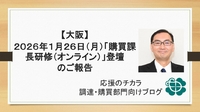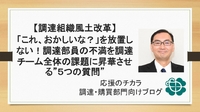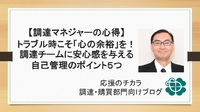- ホーム
- ブログ
- 「調達・購買部門」関連記事
- 【調達マネジャー必見!】調達・購買部門の組織づくりに役立つ「ダンバー数」とは?
【調達マネジャー必見!】調達・購買部門の組織づくりに役立つ「ダンバー数」とは?
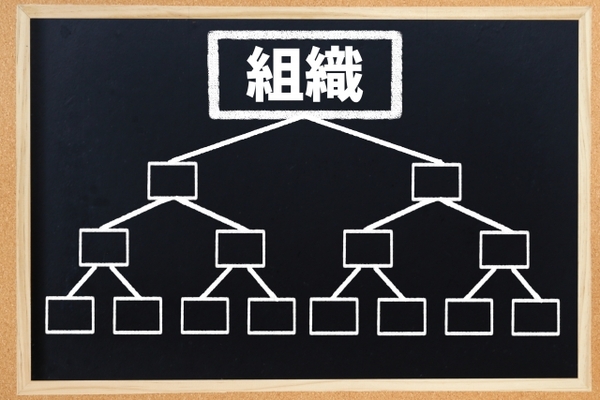
- 調達・購買部門でマネジャーをしているが・・・。
- 目先の対応に追われて部下の育成指導まで行き届かず困っている・・・。
- どうしたら部下の育成指導の時間を取ることができるか教えてほしい!
部下の育成・指導についてお悩みの調達マネジャーの方へ。目先の調整やトラブル対応にばかり追われてしまい、部下一人一人に目をかけることができず、育成・指導が後回しにという状態をなんとかしたいですよね。
もしかしたら、その問題は、「組織やチームの人数」を調整することで解決できるかもしれません。
今回は、【調達マネジャー必見!】調達・購買部門の組織づくりに役立つ「ダンバー数」とは?についてお伝えしますので、ぜひご覧ください。
【調達マネジャー必見!】調達・購買部門の組織づくりに役立つ「ダンバー数」とは?
「ダンバー数」とは?
まずは、「ダンバー数」について確認いきましょう。
ダンバー数理論とは、イギリスの人類学者ロビン・ダンバーが提唱した、人が親密な人間関係を維持できる人数の上限に関する理論です。ダンバーは、平均的な人間の脳の大きさを計算し、霊長類の結果から推定する事によって、人間が円滑に安定して維持できる関係は150人程度であると提唱しています。
この理論を組織作りに生かした場合、例えばオフィスの人数を150人を上限としたり、チームの規模を5人、15人、50人、150人を上限とするといったことです。
また、人数によって親密度に特徴があり、人間関係を例にしてご紹介します。
①3人~5人(もっとも親しい親友)
価値観や性格、感情、行動様式に至るまでもっとも深く理解・信頼し合い、会っていなくても分かり合える親密度であり、お互いに本音を言っても受け入れてくれると思えます。相手の感情の動きや行動が予測でき、コミュニケーションは阿吽の呼吸、アイコンタクトで通じ合える関係性です。
②5〜15人(もっとも親しい親友の外側にある交友関係)
話したことがない人も出てきます。顔と名前くらいは知っていて久しぶりに会っても挨拶はできます。学校で言えばクラスメイトに相当します。例えば文化祭でクラスで何かやろうとすると様々な価値観や考え方が露見して、簡単にはまとまらないという人数です。
本音を言い合うことはまずなく、相手の感情や行動の予測はかなり難しく、阿吽の呼吸やアイコンタクトではコミュニケーションが成り立たず、コミュニケーションを取っていくことが必要な関係性です。
③50〜150人(さらに外側にある人間関係)
学校で言えば一学年の人数です。顔と名前が一致する人数には限界があり、一致しない人が出始めます。話したことがない人も多数いますので、話したことがなければ人間関係は築けません。学校で会っても、挨拶したりしなかったり。相互理解、相互信頼に基づく協力関係はほとんど期待できない人数です。
調達マネジャーがマネジメントする際の最適な人数は?
では、ダンバー数理論を応用した場合、調達マネジャーがマネジメントする際の最適な人数について見ていきましょう。
おすすめは、組織の最小単位を5人にすることです。5人を目安にチーム編成することで、メンバー一人一人の動きを観察しながらフォローすることができるため、部下の育成指導にも時間をかけてできるようになります。
もし、調達マネジャーさんが所属するチームの人数が5人以上の場合は、調達マネジャーさんが直接フォローできる人数を5人程度とし、その他のメンバーはまとめ役のリーダーがフォローするという体制にするなど調整することができればマネジメントしやすくなります。
関係部門との調整も5人を目安にする
関係部門との調整についても応用が可能です。
調達・購買部門と関わりのある関係部門の人数を把握して、人数が多い場合は、関係部門ごとにキーマンとなる人を中心に相互理解、関係性を深めていくことができれば、調整もスムーズになります。例えば以下のとおりです。
関係部門との調整(例)
- 技術部門(技術部長、技術課長、リーダー、キーメンバーなど5人に絞る)
- 生産部門(生産部長、生産課長、リーダー、キーメンバーなど5人に絞る)
- 営業部門(営業部長、営業課長、リーダー、キーメンバーなど5人に絞る)
まとめ
- ダンバー数理論とは、人が親密な人間関係を維持できる人数の上限に関する理論である
- 組織の最小単位を5人にすることで部下の育成指導にも目を向けることができるようになる
- 関係部門との調整も5人を目安に相互理解、関係性を深めていく
調達マネジャーさんが一人でマネジメントできる人数には限界があります。ダンバー数理論を参考にしていただきながら、最適なマネジメント環境づくりへ向けて見直してみてはいかがでしょうか。
調達・購買部門の部門長様・調達マネジャー様向けに「調達・購買部門の人材育成」に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
お問い合わせフォーム関連エントリー
-
 【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
-
 【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
-
 【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
-
 【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
-
 【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら