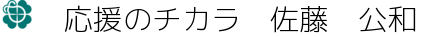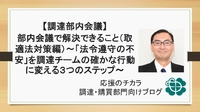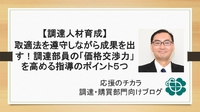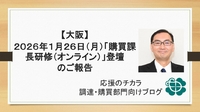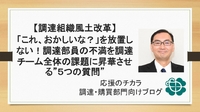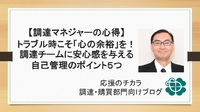- ホーム
- ブログ
- 「企業研修」関連記事
- 【研修担当者向け】「部門特性の違い」を理解した上で部門間調整するポイントとは?
【研修担当者向け】「部門特性の違い」を理解した上で部門間調整するポイントとは?

- 若手社員向けの研修を検討していて・・・。
- 関係部門との調整力を高める内容を取り入れたいが・・・。
- どのような内容にすればいいか教えてほしい!
このような悩みをお持ちの研修担当者の方へ。
関係部門との調整力を高めるためにどのような研修内容にすればいいか悩みますよね。
応援のチカラの研修では、関係部門との調整力を高めるためには、関係部門の「特性の違い」を理解した上で調整することが大切ですとお伝えしています。
【研修担当者向け】「部門特性の違い」を理解した上で部門間調整するポイントとは?
関係部門との調整力を高めるためにまずやるべきことは「部門特性の違い」を理解すること
関係部門との調整力を高めるために、まず初めにやるべきことは、「部門特性の違い」を理解することです。
部門特性の違いとは、
- 部門が「目指すゴール」や「仕事の優先順位の違い」
のことです。
例えば、以下のとおりです。
関係部門の特性(例)
- 営業部門の特性「売上をアップさせたい」「顧客の要望に応えてリピートにつなげたい」
- 技術部門の特性「顧客が要望に対応できる仕様書をつくりたい」
- 生産部門の特性「計画通りに稼働させたい」「棚卸在庫を減らしたい」
- 調達部門の特性「コスト削減をしたい」
このように同じ組織であっても、部門ごとに目指すゴールが異なりますので、
- 同じ組織でも部門ごとに目指すゴールが異なる
- 部門ごとに仕事の優先順位が異なる
- 関係部門に仕事を依頼するときのコミュニケーションの取り方には工夫が必要になる
- 関係部門との調整力を高めるには「部門特性の違い」を理解することが重要
「部門特性の違い」を理解した上で部門間調整するポイントとは?
それでは、「部門特性の違い」を理解した上で部門間調整するポイントについて見ていきましょう。
ポイント① 関係部門が目指している部門目標を確認する
1つ目は、関係部門が目指している部門目標を確認することです。「部門特性の違い」は「部門目標の違い」から生まれます。まずここから確認していきます。
ポイント② 関係部門における優先順位の高い仕事を確認する
2つ目は、関係部門における優先順位の高い仕事を確認することです。優先順位の高い仕事とは、「目標を実現するためにすべきこと(施策)」です。次にこの点について確認していきます。
ポイント③ 優先順位の高い仕事が進められるように協力する
3つ目は、優先順位の高い仕事(目標を実現するためにすべき施策)が進められるように協力することです。協力とは、自分たちの部門でできることで協力することです。例えば、調達部門が生産部門に協力する場合、「生産計画どおりに進められるよう、取引先との納期調整をがんばる」といった感じです。協力することでお互いに協力し合うという関係づくりにつなげていくための最初の一歩を踏み出します。
ポイント④ 関係部門にとって優先順位の低い仕事を依頼するときは配慮する
4つ目は、関係部門にとって優先順位の低い仕事を依頼するときは配慮することです。部門目標を実現することに直接つながらない仕事を引き受ける場合、関係部門に配慮して依頼する必要があります。配慮するポイントは、以下のとおりです。
- 丸投げしない(任せきりにしない)
- 仕事を進める上で必要な情報や依頼理由などを丁寧に説明する
- 対応してもらえたら感謝の気持ちを伝える
まとめ
- 関係部門の特性の違いとは、「部門目標」や「仕事の優先順位」の違いのこと
- 関係部門の特性の違いを理解した上で部門間調整するポイントは4つ
- ポイント①関係部門が目指している部門目標を確認する
- ポイント②関係部門における優先順位の高い仕事を確認する
- ポイント③優先順位の高い仕事が進められるように協力する
- ポイント④関係部門にとって優先順位の低い仕事を依頼するときは配慮する
関係部門の目標と仕事の優先順位の違いを理解する。関係部門にとって優先順位の高い仕事が進められるようにできることで協力関係づくりをする。関係部門にとって優先順位の低い仕事の依頼をするときは配慮する。これが、関係部門と調整するために必要なポイントです。
応援のチカラでは、それぞれのご事情に合わせてカスタマイズした「調整・交渉力向上研修」を実施する可能です。お気軽にお問い合わせください。
研修担当者様、調達マネジャー様向けに「調整・交渉力」に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
ご予約・お問い合わせ関連エントリー
-
 【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
-
 【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
-
 【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
-
 【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
-
 【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら