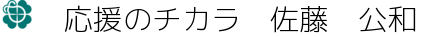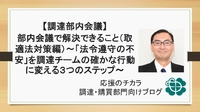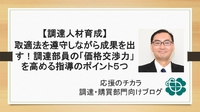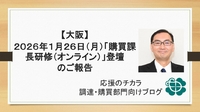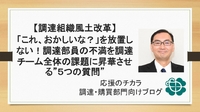- ホーム
- ブログ
- 「部下育成」関連記事
- 他責思考の部下を自責思考に変えるポイント3つ
他責思考の部下を自責思考に変えるポイント3つ

- 問題が起こった時、すぐに他人のせいにする部下がいる・・・。
- 他人や環境のせいにしてばかりで、自ら行動しないので困っている・・・。
- 他責思考の部下を自責思考に変えるポイントを教えて欲しい!
起こった問題を自分事として対応できない部下に「もっと責任感をもって対応してほしい!」と伝えてもなかなか変わらないですよね。でも、変わらない部下がダメなんだと思い続けていると、マネジャー自身が「他責思考」になってしまいます。
こういうときは、コーチングスキルを活用して、他責思考の部下を自責思考に変えるサポートするのが有効です。
今回は、他責思考の部下を自責思考に変えるポイント3つについてお伝えしますので、ぜひご覧ください。
他責思考の部下を自責思考に変えるポイント3つ
自責思考と他責思考の違いとは?
まず、自責思考と他責思考の違いについて見ていきましょう。
- 自責思考とは、物事で問題や失敗が起こった場合、その原因や責任が自分にあると考えること
- 他責思考とは、何か物事で問題や失敗が起こった際、その原因は自分ではなく他人にあると考えること
自責思考の人は、失敗した時にその原因は自分にあると考えることができるので、自分で原因を特定して改善するために行動することができます。
他責思考の人は、失敗した時にその原因は他人にあると考えることによって、自分は悪くないという言い訳や責任逃れをしてしまい、問題が解決されず、さらなるトラブルに発展する場合もあります。
他責思考の部下には自責思考を持って対応できるよう、マネジャーがサポートすることが大切です。
部下を自責思考に変えるポイント3つ
では、部下を自責思考に変えるポイント3つについて見ていきましょう。
ポイント① 部下を認める
1つ目は、部下を認めることです。他責思考の人は、人に指摘されたり責められたりすると、自分は悪くないという「自己防衛」の心理が働いて他人のせいにしてしまいますので、まずは、部下の仕事ぶりを認めることから始めましょう。
もし、部下の行動が問題の原因になっていたとしてもいったん認めることで、責められることはないという安心感を持ち、マネジャーの話を聴く準備ができるようになります。
部下を認めるポイントについては、関連記事「部下のやる気を引き出す5つの承認レベル」を合わせてご覧ください。
【関連記事】「部下のやる気を引き出す5つの承認レベルとは?」
部下のやる気を引き出す5つの承認レベルとは?
つい、“結果がよければ褒める、ダメだったら叱る”をやってしまい、自己嫌悪になってしまう・・・。部下を褒めて伸ばしたいけど、なにをどう褒めていいかわからない・・・。部下のやる気を引き出すために声かけしたいけど、どんなふうに声かけしたらいいか...
ポイント② 部下に手本を示す
2つ目は、部下に手本を示すことです。手本を示すというのは、「自責思考で行動するということはこういうことですよ」というマネジャーの姿を見せることです。おすすめは、部下と同じ目線に立って、同じ時期に何をしていたのかについて伝えることです。
(例)
- 他責思考で仕事をしていたことでお客様に迷惑をかけてしまったことがあり、以後気をつけるようにしているといった経験談を伝える
- 当時の上司から自責思考の考え方について指導されたことを伝える
- 普段、自責思考で心がけている考え方や取り組む姿勢について伝える
ポイント③ コーチングの質問スキルを活用してサポートをする
3つ目は、コーチングの質問スキルを活用してサポートすることです。
(質問例)
- 「もし、この問題が自分たちにも原因があるとしたらどんなことがあるかな?」
- 「自分たちが行動することで問題が解決するとしたらどんな方法があるかな?」
最初はなかなか答えが出てこないかもしれません。そんなときは、考え方や答えの出し方のヒントを伝えながら一緒に考えていきましょう。そういった機会を繰り返していくうちに自責思考を身につけることができるようになります。
まとめ
- 自責思考と他責思考の違いは、物事で問題や失敗が起こった場合、その原因や責任が自分にあると考えるか他人にあると考えるかの差である
- 部下を自責思考に変えるポイント①は、部下を認めて、マネジャーの話を聴く準備してもらう
- 部下を自責思考に変えるポイント②は、部下に手本を示して、自責思考とはどんなものなのかを理解してもらう
- 部下を自責思考に変えるポイント③は、コーチングの質問スキルを活用して自責思考に変えるサポートをする
コーチングスキルを活用して、問題や失敗が起こった原因と問題解決するためのプロセスを一緒に話し合うことから始めましょう。原因を特定して、問題を解決する方法を自分で考え行動できるようになれば、おのずと自責思考に変わっていきますよ。
新型コロナウイルスの影響が続く中、人事部が積極的に従業員のモチベーション向上に関わり、従業員満足度の向上につなげていきたいとお考えの人事部様、研修担当者様向けに「部下のモチベーションアップ」研修に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
ご予約・お問い合わせ関連エントリー
-
 【名古屋】2026年2月13日(金)「製造業における若手社員のための「報連相」と「聴き方・メモの取り方」習得セミナー」登壇のお知らせ
「上司からの指示をメモに取っているつもりだが、後で見返すと不明点が出てきたり、聞き逃しによる作業のやり直しが発
【名古屋】2026年2月13日(金)「製造業における若手社員のための「報連相」と「聴き方・メモの取り方」習得セミナー」登壇のお知らせ
「上司からの指示をメモに取っているつもりだが、後で見返すと不明点が出てきたり、聞き逃しによる作業のやり直しが発
-
 【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
-
 【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
-
 【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
-
 【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら