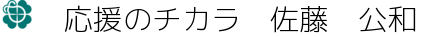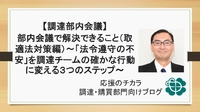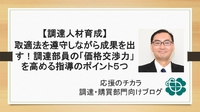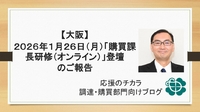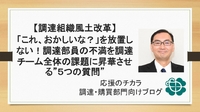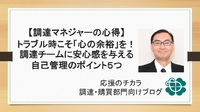- ホーム
- ブログ
- 「モチベーション」関連記事
- 若手社員の内的動機づけを促す3つの欲求とは?
若手社員の内的動機づけを促す3つの欲求とは?

「内的動機づけが大事なのはわかった。」
「でも、内的動機づけは本人の内側から湧いてくるものなのに、どうやって外部から促してあげたらいいのかな?」
「とくに、若手社員に対して周囲の人はどのように接してあげたらいいのだろう・・・。」
今年の「新入社員研修」や「若手社員研修」の内容について検討中の人事課長の方へ。
今回は、「新入社員研修」や「若手社員研修」で、内的動機づけを促すための欠かせない自己決定理論の土台となる内的動機づけを刺激する3つの欲求についてお伝えしてきますので、ぜひご覧ください。
若手社員の内的動機づけを促す3つの欲求とは?
内的動機づけについては、人事課長が知っておきたい2種類のモチベーションとは?
自己決定理論の概要については、やる気のある人材とやる気のない人材の違いとは?
それぞれのブログ記事をご確認ください。
自己決定理論の土台を支える3つの基本欲求とは?
自己決定理論の土台を支えるのは3つの基本欲求、それが「有能感」「関係性」「自律性」です。
- 「有能感」は自分の能力とその証明に対する欲求
- 「関係性」は周囲との関係に対する欲求
- 「自律性」は自己の行動を自分自身で決めることに対する欲求
特に「自律性」の欲求が重要だとされています。
これら3つの欲求が満たされていくことで、人は内的動機づけや心理的適応を促進させていきます。
3つの基本欲求の高め方
では、3つの基本欲求を高めるにはどうしたらいいでしょうか?
「自律性」「有能感」「関係性」のそれぞれ高め方を見ていきましょう。
自律性を高める
自律性とは、自己決定や自主的な行動のことです。この自律性を高めるには、行動を選択する機会を増やし、行動を選択していることを本人に認識させることが効果的です。また、社員自身が行動の主体であることを気づかせるような問いかけ・助言、サポートを行うことが大切です。「○○について、Aさんはどう考えているの?」「この案件について、わが社の企業理念から考えるとどんな取り組みが必要かな?」「今、Bくんの目標達成率は60%だと思うんだけど、これからどんな取り組みをしていきたい?」など、主体性を引き出し、自律を実感できる関わり合いが自律性を高めます。
有能感を高める
有能感とは、自分が有能でありたいという思いや有能さを感じられることです。有能感を高めるには、自らの行動が成果につながっていることを認識してもらうことが重要です。仕事を成し遂げた結果として、顧客に喜んでもらえたことや、社内で表彰されるといったことは、社員の有能感を高めます。
関係性を高める
関係性とは、他者から尊敬されることや他者との連帯感です。関係性を高めるには、部署やチーム内での継続的なサポート等、社員に自分その組織の一員であることを感じさせることが重要です。この関係性が高まると、組織への貢献意欲が高まったり、会社や組織のミッションを理解したうえで行動したりするといった効果があります。この関係性は、承認欲求が強い若手社員にとっては効果的なポイントです。新入社員研修・若手社員研修で内的動機づけを促すポイント
最後に、私が研修講師として新入社員研修・若手社員研修を行う上で、内的動機づけを促すために意識しているポイントについてご紹介していきます。
自律性を促す工夫
講師からの説明を聞いて理解するだけでなく、自ら選択して行動する機会を増やすことが効果的です。例えば、ケーススタディで自分の考えを発表する機会をもつといったことです。受講される方の人数にもよりますが、研修を行う際は少なくとも一人一回は発表してしていただく機会を用意するようにしています。
有能感を高める工夫
ペアワークを行う際には、お互いにフィードバックする機会を用意するようにしています。「自分は学んだことを実践できた、身につけられた」と実感することで、私はできるという自信を養うことができます。
関係性を高める工夫
研修でケーススタディやグループディスカッション、プレゼンなどを行う際には、チームごとに発表してもらう機会を用意するようにしています。メンバーで協力してチーム同士で切磋琢磨できるよう「ゲーム実習」「クイズ演習」などを取り入れるのも効果的です。
まとめ
- 内的動機づけを促す欲求は「自律性」「有能感」「関係性」
- 「自律性」は選択機会を増やし、「有能感」は成果を認識させ、「関係性」は、組織の一員であることを認識させて高める
- 研修では、「ワーク等で主体性を発揮する機会を持つ」「学んだことを実践できたという自信を養う」「メンバーと協力して演習に取り組む」機会を持つ
内的動機づけを組織として育むことは、社員一人一人の創造力を引き出し、柔軟でクリエイティブな組織づくりに大きく貢献します。特に、学校教育という受け身の組織の中で過ごしてきた新人や若手社員は、内的な動機を見出す姿勢を身につけることが自律を促すカギになります。
新型コロナウイルスの影響が続く中、人事部が積極的に従業員のモチベーション向上に関わり、従業員満足度の向上につなげていきたいとお考えの人事部様、研修担当者様向けに「部下のモチベーション向上」研修に関するご相談を無料でお受けしています。
関連エントリー
-
 【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
【調達部内会議】部内会議で解決できること(取適法対策編)〜「法令遵守の不安」を調達チームの確かな行動に変える3つのステップ〜
「取適法への対応が必要なのは理解しているが、具体的に現場の調達部員にどのような指示を出し、どこまで徹底させる
-
 【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
【調達人材育成】取適法を遵守しながら成果を出す!調達部員の「価格交渉力」を高める指導のポイント5つ
「取適法で『買いたたき』などの禁止事項が強化され、調達部員にどこまで踏み込んだ価格交渉をさせてよいのか、その
-
 【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
【大阪】2026年1月26日(月)「購買課長研修(オンライン)」登壇のご報告
調達部員に任せきりの『個人プレー』が目立ち、トラブルが起きるまで状況を把握できないことが多くて不安を感じている
-
 【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
【調達組織風土改革】「これ、おかしいな?」を放置しない!調達部員の不満を調達チーム全体の課題に昇華させる”5つの質問”
「調達部員が現場で『このやり方は非効率だ』と感じていても、それが単なる不満や愚痴として流されてしまい、調達チ
-
 【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
【調達マネジャーの心得】トラブル時こそ「心の余裕」を!調達チームに安心感を与える自己管理のポイント5つ
「トラブルが重なると、つい感情的になり、調達部員に対して強い口調で接してしまったあとに後悔してしまう。・・・
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら